

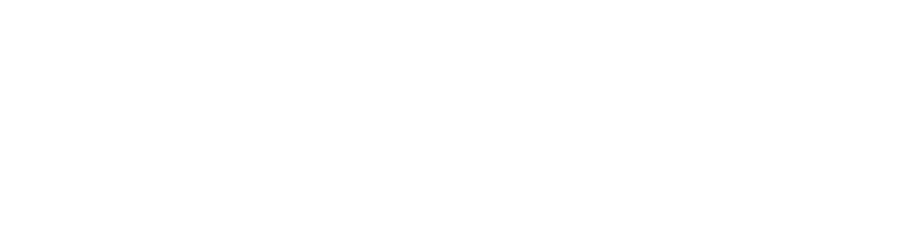


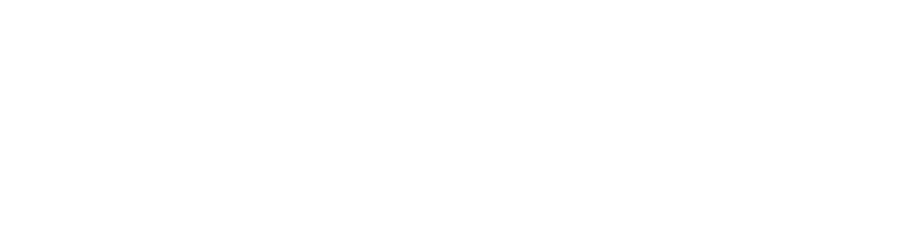


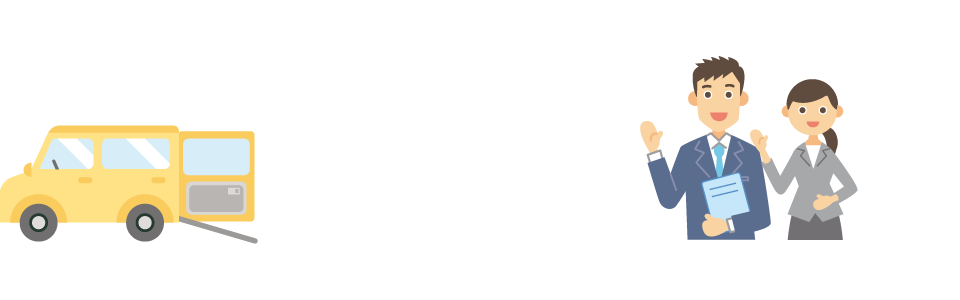
こんにちは!
近年、介護サービスの選択肢が増える中で、「小規模多機能型居宅介護(以下、小規模多機能)」という言葉を耳にする機会が増えた方も多いのではないでしょうか?
「デイサービスや訪問介護と何が違うの?」「どんな人に向いているの?」と疑問を持つ方も多いと思います。
この記事では、小規模多機能の特徴やメリット・デメリット、利用対象者について詳しく解説します。この記事を読むことで、小規模多機能の仕組みがよく分かり、自分や家族にとって適した介護サービスかどうか判断しやすくなります。
小規模多機能とは、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けることを目的とした地域密着型サービスです。施設に通う「通い(デイサービス)」を中心に、必要に応じて「泊まり(ショートステイ)」や「訪問(ホームヘルプ)」のサービスを受けることができます。
一般的な介護施設と異なり、利用者ごとのニーズに合わせた柔軟な対応が可能で、顔なじみのスタッフが一貫してケアを担当します。そのため、認知症の方や要介護度が進行している方でも安心して利用できるサービスとなっています。
利用者は、日中に施設へ通い、食事や入浴、レクリエーションなどの介護サービスを受けることができます。一般的なデイサービスと異なり、時間の制約が少なく、長時間の利用が可能です。
スタッフが利用者の自宅に訪問し、食事介助や入浴介助、掃除、買い物の支援などを行います。訪問介護と似ていますが、訪問回数や時間に柔軟に対応できる点が特徴です。
家族の急な用事や体調不良の際に、利用者が施設に宿泊することができます。計画的な利用だけでなく、急な事情にも対応できるため、家族にとっても安心できるサービスです。
小規模多機能は、「通い」「訪問」「泊まり」を利用者の状況に応じて自由に組み合わせることができます。例えば、「普段はデイサービスを利用しているが、体調が悪い日は自宅で訪問介護を受けたい」「家族が旅行に行く間だけショートステイを利用したい」など、個々のニーズに対応できます。
小規模多機能では、登録制のため、限られた人数のスタッフがケアを担当します。そのため、利用者とスタッフの関係が築きやすく、安心して介護を受けることができます。認知症の方にとっても、環境の変化が少ないため安心感があり、落ち着いた生活を送ることができます。
小規模多機能は、利用者が住む地域内で運営されるため、地域とのつながりを保ちながら生活を続けることができます。施設への送迎がスムーズで、家族も通いやすい点がメリットです。
一般の介護サービスでは、デイサービスと訪問介護、ショートステイが別々の施設で提供されることが多いため、異なるスタッフが対応します。しかし、小規模多機能では同じスタッフが担当するため、利用者にとって安心感があります。
急な泊まりや訪問にも対応できるため、家族の負担が大きく軽減されます。特に、在宅介護を続けたい家族にとっては、大きな支えとなるでしょう。
小規模多機能は、利用者の体調や生活状況に合わせた介護ができるため、安心して生活を続けることができます。
小規模多機能は1施設あたりの登録定員が最大29名と決まっているため、希望しても利用できないことがあります。
小規模多機能は、医療依存度が高い利用者への対応が難しい場合があります。たとえば、常時点滴が必要な方や、気管切開が必要な方などは、医療機関との連携が必要となるため、事前に確認することが大切です。
小規模多機能を利用すると、他のデイサービスや訪問介護を利用することができません。そのため、すでに特定の施設を利用している場合は、乗り換えが必要になります。
小規模多機能は、「通い」「訪問」「泊まり」を自由に組み合わせられる柔軟な介護サービスです。利用者の状況に応じたケアを提供し、家族の負担を軽減できる点が大きな魅力です。
利用を検討する際は、地域の小規模多機能施設に相談し、施設の雰囲気や対応可能な範囲を確認してみるのがおすすめです。住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、小規模多機能をうまく活用しましょう!
