

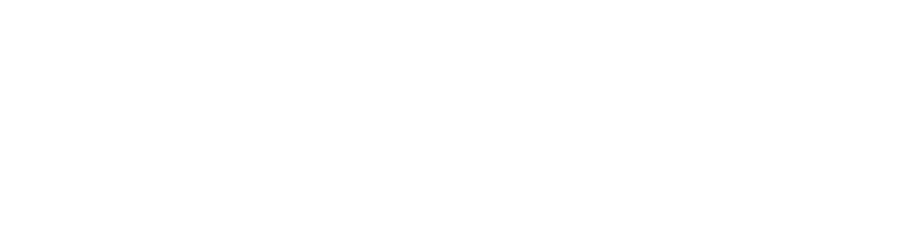


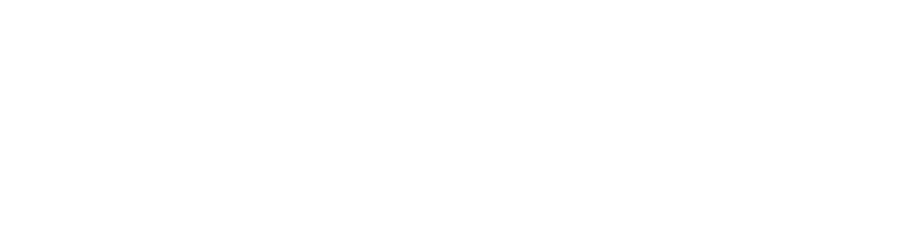


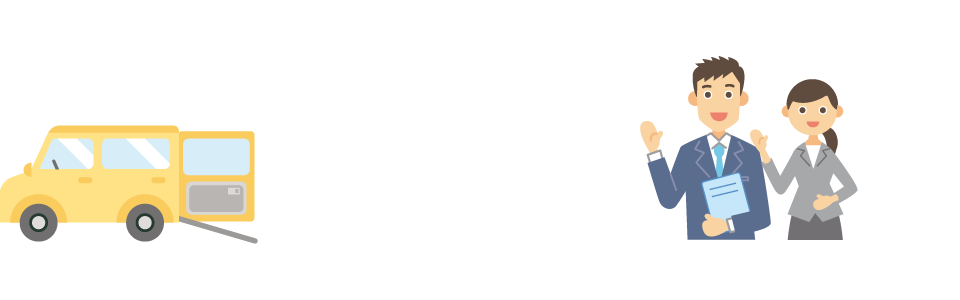
こんにちは!
「介護認定によってどのようなサービスが受けられるのか?」「要支援1と要介護5では実際どれほどの違いがあるのか?」という疑問を持つ方は多いです。
この記事では、介護保険制度の中での要支援・要介護の違いと、それに応じたサービス内容、支給限度額(保険で使える金額)の違いを詳しく解説します。
最後まで読むことで、自分や家族に必要な介護レベルがどこか、どのようなサービスを受けられるのか、そしてどれくらいの費用支援があるのかが明確に理解できるようになります。
高齢者の家族を介護中の方や、これから介護申請を考えている方には必見の内容です。
介護保険制度は、原則40歳以上の人が加入し、介護が必要になったときにサービスを利用できる仕組みです。認定を受けることで、在宅や施設での介護サービスを1割〜3割の自己負担で受けることが可能になります。
介護認定は「要支援1・2」と「要介護1〜5」の7段階に分かれています。要支援は自立度が高く、主に介護予防目的の支援を受けます。一方、要介護は日常生活に介助が必要な状態であり、介護量に応じて段階が細かく設定されています。
申請後、市町村が訪問調査と主治医意見書をもとに、全国共通のコンピュータ判定と介護認定審査会により判定されます。評価項目には、身体能力、生活動作、認知機能、コミュニケーション力、精神状態などが含まれています。
要支援1では、主に介護予防を目的としたサービスが提供されます。具体的には、掃除や買い物などの生活援助型の訪問サービス、軽度の運動やリハビリを目的とした通所型サービス(デイサービス)があります。
支給限度額は月額50,320円(2024年度時点)。この範囲内で複数のサービスを組み合わせて利用可能です。自己負担は原則1割(一定所得以上の方は2〜3割)です。
要支援2になると、支援の量や頻度が増えます。訪問介護の回数も増え、デイサービスでの入浴支援や集団機能訓練などの内容も充実します。
支給限度額は105,310円。要支援1の倍以上となり、より柔軟な介護予防サービスの選択が可能になります。
要支援の段階では、ケアマネジャーではなく「地域包括支援センター」が中心となってケアプランを作成します。介護予防プランは、状態の悪化を防ぎ、自立を促進することが目的です。
要介護1では、部分的な身体介護(入浴、排泄介助など)と生活援助の両方が提供されます。支給限度額は166,920円。
訪問介護、通所介護、短期入所(ショートステイ)など、要支援と比べて多様なサービスを利用できます。
要介護2では、歩行や移動の支援が必要なケースが多くなります。通所系サービスに加え、福祉用具貸与や住宅改修なども活用されます。
支給限度額は196,160円。サービス内容の選択肢がさらに広がります。
要介護3は、日常生活の大部分で介助が必要です。介護量が大きくなり、特別養護老人ホームなどの入所も検討され始めます。
支給限度額は269,310円。訪問介護や夜間対応型訪問サービスなどの高頻度利用が可能です。
要介護4は、移動・食事・排泄などほぼ全ての動作に介助が必要な状態です。認知症や寝たきり状態の方も多く、24時間の見守りが必要になることもあります。
支給限度額は308,060円。医療系サービス(訪問看護など)の利用も多くなります。
要介護5は、介護保険で認定される中で最も重度の状態です。常時介護が必要で、自力での移動・排泄・食事は困難です。
支給限度額は360,650円。介護保険サービスの上限まで利用できるため、重度対応型施設や看取り支援なども選択可能です。
要支援から要介護に移行すると、サービスの「質」と「量」が大きく変化します。要支援では「生活援助」が中心ですが、要介護では「身体介護」が主となり、医療的ケアや夜間対応などにもアクセス可能になります。
支給限度額の差は非常に大きく、要支援1の約5万円に対し、要介護5では約36万円。これにより、利用できるサービスの範囲と回数が圧倒的に広がります。
介護度が高まるほど、サービスの利用頻度は増えますが、同時に家族の精神的・身体的負担も増します。介護認定が適切であれば、公的サービスを活用しながら、在宅介護の負担を軽減することが可能です。
認定調査では、「良いときの状態」ではなく「普段困っている状態」を明確に伝えることが重要です。遠慮せず、困難な点を具体的に話すことが正確な評価につながります。
主治医の意見書には、病状や日常生活への影響が記載されます。医師が正確に状況を把握しやすいよう、事前に家族からの情報提供も行うと良いです。
「実際の介護負担に対して認定が軽すぎる」と感じた場合は、不服申し立てや区分変更申請を行うことができます。状況の変化に応じて、早めに再申請することが大切です。
介護認定による「評価の違い」は、受けられるサービス内容、利用可能な金額、家族の負担など多方面にわたって大きな影響を与えます。
要支援1と要介護5では、支給限度額で7倍以上の差があり、サービスの種類・質・回数にも顕著な違いが見られます。適切な認定を受けることで、介護の質を向上させ、家族の負担軽減にもつながります。
今後の介護生活を見据えて、制度の仕組みを理解し、必要に応じた支援や申請をしっかりと行っていくことが重要です。
