

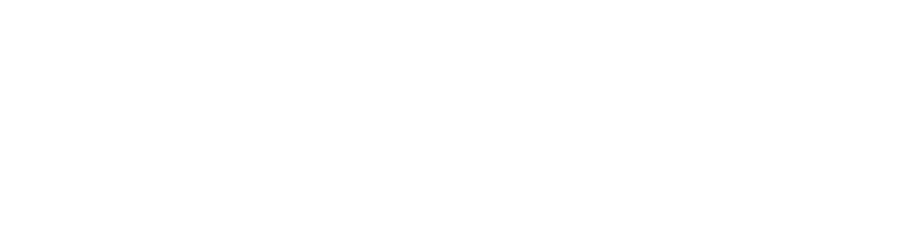


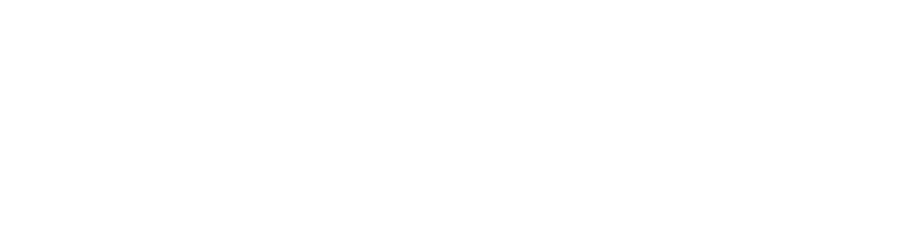


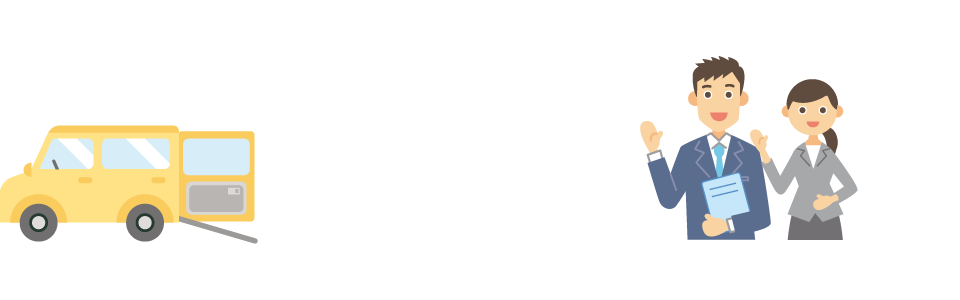
暑い季節や乾燥する冬場、体調を崩しがちなときにも重要になるのが「水分補給」です。特に乳幼児や高齢者は、脱水や熱中症になりやすいリスク層とされており、日頃から意識的な水分摂取が求められます。しかし、年齢や体調によって必要な水分量や補給のタイミング・方法は異なります。
本記事では、乳幼児から高齢者までの年齢別に適した水分補給のポイントをわかりやすく解説します。家族みんなで健康に過ごすための参考にしてください。
人間の体の大部分は水分で構成されており、乳児では約75〜80%、成人で約60%、高齢者では約50〜55%が水分です。この割合は年齢と共に減少し、また、体内の水分保持機能や「のどの渇き」を感じる感覚も衰えていきます。
そのため、同じ「水分補給」でも、年齢によって意識すべきタイミングや方法が変わってくるのです。
体内水分率が非常に高く、代謝も活発。
発汗や発熱、下痢などで脱水を起こしやすい。
自分で「のどが渇いた」と訴えることが難しい。
30〜50mlずつ、こまめに与えるのが基本。
湯冷まし、麦茶、白湯などカフェイン・糖分の少ないものを。
母乳・ミルクだけでなく、離乳食以降は水分補給の意識をプラス。
発熱・下痢時は経口補水液(OS-1など)を活用。
熱中症の初期症状に気付きにくいので、顔の赤み・ぐったり感・尿の回数減少などを観察。
一度に多く与えると嘔吐の原因にもなるため、少量ずつ与えるのが基本です。
活動量が多く、部活や外遊びなどで汗をかく時間が長い。
遊びに夢中で水分補給を忘れがち。
「のどが渇く前に飲む」習慣づけが重要。
学校に水筒を持たせ、休み時間・登校前・下校後・就寝前に飲ませる。
スポーツ時は水+塩分補給が必要 → スポーツドリンクを2倍に薄めて使用もおすすめ。
市販のジュースやスポーツ飲料は糖分が高いため、摂りすぎ注意。
自宅では麦茶やミネラルウォーターなどを中心に。
代謝が落ちることで水分摂取量も減りがち。
忙しさやストレスで水分摂取を忘れることも多い。
1日1.5L〜2Lを目安にこまめに摂取。
朝起きた時、食事中、運動前後、入浴前後、就寝前が水分補給のタイミング。
常に水筒やペットボトルを手元に置いておくと無意識に飲む習慣がつく。
コーヒーや紅茶、アルコールには利尿作用があるため、水分補給とはカウントしない。
デスクワーク中心の人は特に意識的に水を摂るようにしましょう。
体内の水分量が少なくなり、のどの渇きに気づきにくい。
腎機能や代謝機能の低下により、水分の保持能力が低下。
トイレが近くなるのを嫌い、水分を控える傾向も。
1日1,200〜1,500mlが目安。
**「時間を決めて飲む」**ことで習慣化(起床後・朝食後・昼食後・夕食後・就寝前など)。
白湯やぬるめのお茶など、温度や風味に変化をつけて飲みやすく。
果物やスープなど食事からの水分も活用。
夜間のトイレを気にして水を控えすぎるのは危険。
軽度の脱水でもふらつき・転倒・認知症の進行に関わる可能性があるため、家族の声かけが重要。
利尿剤や糖尿病薬の使用により脱水しやすい。
飲み込む力が低下している場合も。
ゼリー飲料やとろみ飲料を活用すると安全。
介護者が声かけ+定時の水分補給を意識する。
摂取記録表をつけて1日の水分量を把握。
| タイミング | 目安量 | 目的 |
|---|---|---|
| 起床後 | 200ml | 就寝中の発汗による脱水の回復 |
| 食事中 | 各150〜200ml | 食事の水分補給+消化促進 |
| 入浴前後 | 各200ml | 発汗に備える+風呂上がりの脱水回避 |
| 運動時 | 前後に各200ml+途中100mlずつ | パフォーマンスの維持+熱中症予防 |
| 就寝前 | 100〜150ml | 就寝中の水分補給+血液の粘性低下 |
渇きを感じてから一気に大量に飲む → 胃に負担がかかる
アルコールやカフェインを「水分」とカウント → 利尿作用で逆効果
糖分の多い清涼飲料水を日常的に摂取 → 肥満や糖尿病リスク
「トイレが近くなるから」と飲まない → 高齢者に多く、脱水・便秘・転倒を招く
水分補給は単に「のどが渇いたから飲む」だけでは不十分です。年齢によって体の水分構成や感覚機能が異なり、それぞれに合った補給方法が必要となります。
とくに子ども、高齢者、要介護の方は自分から水を求めない場合が多く、周囲の大人の「見守り」と「声かけ」が大切です。
毎日の生活の中で、無理なく・こまめに・楽しく水分補給ができる習慣を作っていきましょう。
※この情報は一般的な健康管理を目的としたものであり、疾患や治療中の方はかかりつけ医や専門家にご相談ください。
