

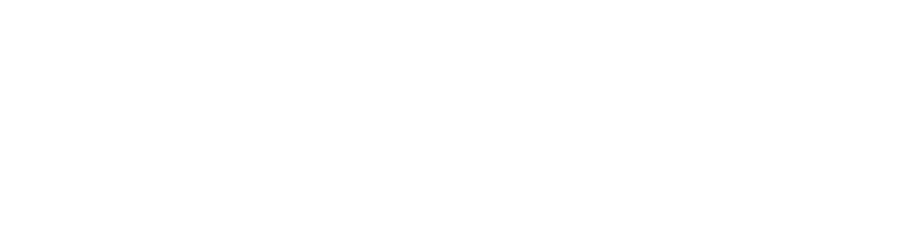


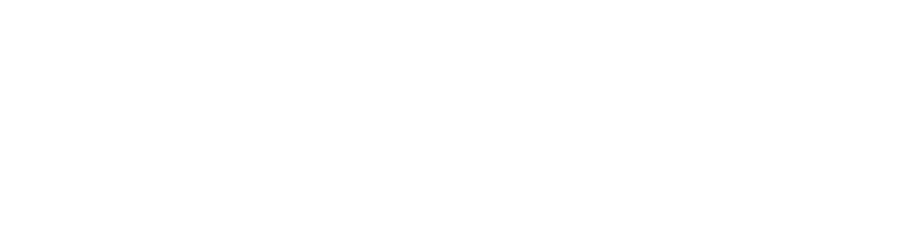


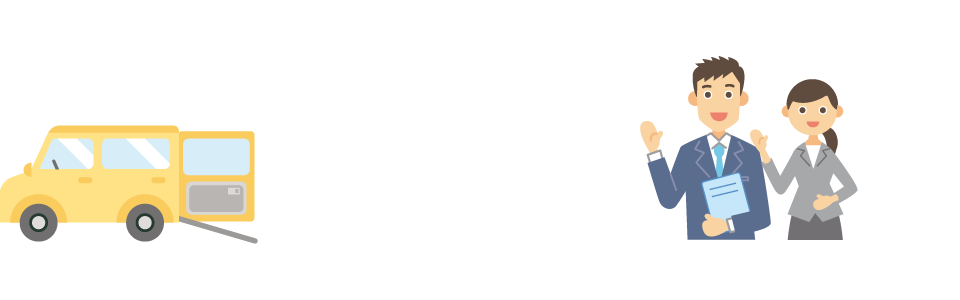
こんにちは!
毎年夏が近づくと、暑さによる体調不良が心配になる方も多いのではないでしょうか。特に高齢者は、加齢による体の変化や持病の影響から、暑さに対する耐性が低下しがちです。そのため、夏の季節には特に注意が必要です。
この記事では、高齢者が安全かつ健康的に夏を過ごすために必要な注意点を、分かりやすく具体的に解説します。熱中症や脱水症状を防ぐための生活習慣、食事・水分補給のポイント、生活環境の整え方、さらにはご家族や介護者ができるサポート方法まで網羅しています。
ご家族の健康を守りたい方、ご自身の体調管理を意識している高齢の方、また高齢者支援に携わる介護職の方にも役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。
高齢者は年齢とともに汗腺の働きが弱まり、体温を調整するための汗をかきにくくなります。その結果、体内に熱がこもりやすくなり、気温がそれほど高くなくても体温が上がってしまう危険があります。さらに、皮膚の感覚も鈍くなり、外の暑さを正確に感じにくくなる傾向もあります。
年齢を重ねると、身体の水分量が減少するだけでなく、喉の渇きを感じる感覚も鈍くなります。そのため、水分が不足していても自覚できず、脱水症状や熱中症に繋がってしまうケースが多いのです。特に、寝ている間や外出先では水分補給のタイミングを逃しやすいため、意識的な補給が重要です。
高齢者には、高血圧・糖尿病・心疾患などの慢性疾患を持っている方も多くいます。こうした病気の治療で使う薬には利尿作用があるものもあり、体内の水分が失われやすくなります。また、病気そのものが体温調節機能や循環機能に影響を与えることもあります。医師の指導の下で体調管理を行うことが非常に重要です。
外出を控えて自宅にいても、室温が高くなれば熱中症になる危険はあります。特に日本の夏は湿度が高いため、実際の気温以上に体への負担が大きくなります。エアコンは日中だけでなく、夜間や早朝にも適切に使用しましょう。冷えすぎが心配な方は、設定温度を28度程度に保ち、扇風機やサーキュレーターを併用して空気を循環させると効果的です。
水分は「喉が渇いた」と感じる前にこまめに摂るのが基本です。1回に大量の水を飲むのではなく、1日に数回に分けて少しずつ摂取しましょう。朝起きたとき、入浴後、就寝前など、日常のルーティンに組み込むと忘れずに済みます。特に発汗量の多い日には、塩分やミネラルも一緒に補える経口補水液やスポーツドリンクを利用するのも有効です。ただし、糖分の多い飲料は避けましょう。
外出はなるべく気温が上がりきらない早朝や夕方を選び、無理のない範囲で行動しましょう。帽子や日傘、サングラスなどを活用し、直射日光を避ける工夫も重要です。衣類は通気性のよい綿や麻などの素材を選び、白やパステルカラーなど熱を吸収しにくい色を選ぶと快適に過ごせます。保冷剤を首元や脇に当てるなどの熱中症対策グッズも併用しましょう。
暑さで食欲が落ちると、栄養が偏って体力の低下につながります。食欲が低下しがちな夏こそ、ビタミンB1やビタミンC、たんぱく質を意識的に摂ることが大切です。豚肉、納豆、卵、レモン、トマト、きゅうりなど、体を冷やしつつ栄養価の高い食材をうまく組み合わせましょう。
気温と湿度が高い夏は、食品の傷みが早く、食中毒のリスクが高まります。調理後の料理は早めに食べきるようにし、常温保存を避けて冷蔵庫で保存しましょう。生魚や生卵などの生ものは避けるか、信頼できる店舗で購入し、なるべく早く調理・消費することが大切です。手洗いや調理器具の衛生管理も徹底しましょう。
冷たい麺類やゼリーなど、喉越しのよい食品を選びながらも、できるだけ栄養が偏らないよう工夫しましょう。たとえば、冷やしそうめんにゆで卵や刻んだ野菜を加えたり、冷製スープに豆腐や鶏ささみを入れるなど、ひと手間加えることで栄養価がぐっと高まります。酢やレモン、しそなどの香味野菜を使うと、食欲も刺激されます。
冷房が苦手な方は、扇風機との併用で室内の空気を効率よく循環させることができます。扇風機は床に近い場所の冷たい空気を上へ送り、部屋全体の温度を均一に保つのに役立ちます。風が直接体に当たらないように注意しながら、必要に応じて首振り機能やタイマーを利用すると快適に使用できます。
遮光カーテンやすだれ、断熱フィルムを使えば、窓から差し込む直射日光を防ぎ、室内の温度上昇を抑えることができます。特に日中、西日が強く当たる窓には積極的に対策を施しましょう。また、植物を窓の外に置く「グリーンカーテン」も自然な遮熱方法として注目されています。
高温多湿な日本の夏では、室温と同時に湿度管理も重要です。湿度が高いと汗が蒸発しづらくなり、体温が下がりにくくなります。除湿機やエアコンの除湿モードを使って、湿度を40~60%に保つようにしましょう。通気性を良くするために、朝晩の涼しい時間に換気を行うのも効果的です。
高齢者自身が体調の変化に気づきにくいため、家族や介護者がこまめに声をかけて様子を確認することが大切です。「水を飲んだか」「冷房は使っているか」「体がだるくないか」といった簡単な質問で十分です。表情や言動のちょっとした違和感にも注意を払いましょう。
熱中症の初期症状には、めまい、頭痛、吐き気、倦怠感などがあります。こうした症状が出たときに慌てず対応できるよう、救急連絡先、かかりつけ医、服薬情報などをまとめた「緊急対応マニュアル」を用意しておくと安心です。
地域の訪問看護サービスやかかりつけ医と日頃から連絡を取り、夏場に体調を崩した場合の対応を事前に相談しておくことも大切です。医師の指導に基づいた熱中症対策や、病気ごとの注意点を共有することで、安心して夏を過ごす準備が整います。
高齢者が夏に体調を崩しやすいのは、加齢による身体の変化が大きく関わっています。しかし、ポイントを押さえて生活することで、多くのリスクを回避することが可能です。室温・湿度管理、水分補給、バランスの取れた食事、外出時の工夫、そして家族や周囲の見守りと連携によって、安心して夏を乗り越えられます。
この記事を参考に、ひとつひとつの対策を日常生活に取り入れて、高齢者の方々が元気で快適に夏を過ごせるようサポートしていきましょう。
